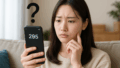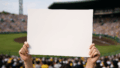万博をめいっぱい楽しむためには、事前準備と心の余裕の両方がとっても大切です。当日はたくさんの人でにぎわう会場の中を歩いたり、さまざまな展示やイベントを楽しんだりと、想像以上に体力も気力も必要になります。そんななか、スムーズに入場できるようにしておくことや、必要な持ち物をしっかり用意しておくことは、安心して楽しい1日を過ごすためのカギになります。
この記事では、空港のように厳しいといわれている手荷物検査の基本的な流れや、検査で引っかからないためのポイント、持って行くと便利なアイテムの紹介、さらに帰り道の混雑をできるだけ避けるためのコツなど、初めて万博に行く方でも安心できるように、やさしく丁寧にまとめています。
ちょっとした準備の差が、当日の満足度を大きく変えてくれます。心にも時間にもゆとりを持って、素敵な思い出をたくさん作れるように、この記事を参考にしながら一緒に準備をしていきましょう♪
- はじめに|万博2025の入場には「空港並みの検査」が待っている
- 大阪・関西万博2025|開催概要とアクセスの基本情報
- 事前に知っておくべき「入場ルール」と検査の流れ
- 検査をスムーズに通過するために今できる準備とは?
- 知らずに持ち込むとNG!事前にチェックしておきたい禁止アイテム
- しっかり準備して最高の1日に!持っていくべき持ち物リスト
- 子ども連れ・高齢者と行く場合のチェックポイント
- スムーズな退場・帰宅のためにできること
- 会場内での過ごし方|楽しむための工夫いろいろ
- 【体験談】実際に行ってみた人の声・気づきまとめ
- 当日の持ち物チェックリスト|印刷して使えるチェック表つき!
- 【Q&A】よくある疑問をまとめて解決!
- まとめ|準備万端で、心にも余裕を持って楽しもう
はじめに|万博2025の入場には「空港並みの検査」が待っている
入場時には、まるで海外旅行の保安検査のようなチェックが行われます。初めてだと少しドキドキしますが、ポイントを押さえれば大丈夫!これから順に解説していきますね。
なぜここまで厳しい?手荷物検査の背景と目的
大阪・関西万博では、日本国内だけでなく世界中からたくさんの方が訪れる予定です。そのため、会場内での安全確保が何よりも大切とされています。大勢の人が一つの場所に集まるイベントでは、ちょっとしたトラブルが大きな混乱につながることもあるため、万全なセキュリティ対策が求められるのです。
特に今回は、国際的な注目を集める博覧会ということもあり、空港と同じような手荷物検査が導入される予定です。金属探知機や目視検査に加えて、一部では持ち物を開けて確認する場面もあるかもしれませんが、これは来場者全員が安心して1日を楽しめるようにするための大切なプロセスです。
「ちょっと面倒だな…」と感じるかもしれませんが、逆にいえばそれだけ安全に配慮されている証拠。心配しすぎず、きちんとルールを理解して準備しておけばスムーズに通過できますよ。
検査で戸惑う人が続出?SNSの声と実際の体験談
先行イベントや他の大規模イベントでは、手荷物検査で戸惑ってしまう人も多かったようです。SNSでは「飲みかけのペットボトルがダメだったなんて知らなかった」「ベルトの金具が反応して焦った」など、予想外の場面に驚く声がちらほら見られました。
中には「並んでいる途中で日差しが強くて熱中症になりかけた」「スマホのQRコードがうまく表示されなくて時間がかかった」など、ちょっとしたことで全体の流れが滞ってしまった例もあります。
これらの体験談からわかるのは、“知っているだけで避けられるトラブル”が多いということ。記事内で紹介する準備ポイントを押さえておけば、そんなトラブルをぐっと減らすことができます。初めての方でも慌てずに行動できるように、一つひとつ確認しておきましょうね。
大阪・関西万博2025|開催概要とアクセスの基本情報

開催場所は夢洲(ゆめしま)!アクセス手段をチェック
会場となる夢洲(ゆめしま)は、大阪湾に浮かぶ美しい人工島で、今後の開発が期待されているエリアです。大阪・関西万博2025の舞台として注目されており、自然と未来が調和する空間として、多くの来場者を迎える準備が進められています。
アクセス手段は主に電車(大阪メトロ中央線の延伸ルート)、臨時のシャトルバス、さらには観光気分が味わえる船便など、多彩なルートが用意されています。公共交通機関の混雑緩和や環境負荷の軽減のため、マイカーより公共交通機関の利用が推奨されています。
また、中央線の延伸開業時期や臨時バスの運行情報などは、時期によって変わる可能性もあるため、公式サイトや交通各社の情報をこまめにチェックするのがおすすめです。混雑時でもスムーズにアクセスするには、早めの行動と代替ルートの確認がカギになりますよ。
開催期間・開場時間・チケット情報まとめ
- 開催期間:2025年4月13日(日)〜10月13日(月)。約半年間にわたって開催される、世界的にも注目されているイベントです。春の心地よい気候に始まり、夏の活気にあふれる催し、秋には紅葉が彩る会場の風景と、季節の移り変わりを楽しみながら、何度訪れても新しい体験ができるのが魅力です。開催期間が長い分、自分のスケジュールに合わせて無理なく予定を立てやすいのもうれしいポイントですね。
- 開場時間:10:00〜21:00(入場最終受付は19:30予定)。午前中から夜までたっぷり楽しめる時間設定で、展示だけでなく、音楽ライブや夜のイルミネーションなど時間帯によって異なる表情を見せてくれる会場の演出も見逃せません。特に夜は幻想的な雰囲気が漂い、ライトアップされた建物やパビリオンがフォトジェニックな空間に早変わり。時間に余裕を持って行動すれば、昼と夜それぞれの魅力をバランスよく堪能できますよ。
- チケット:チケットの種類は、日付指定券・通期パス・平日限定割引券など多岐にわたります。ご家族での訪問、カップルでのデート、おひとりさまの散策など、利用目的や来場頻度に合わせて最適なプランを選びましょう。混雑が予想される祝日や連休は早い段階で完売することがあるので、行きたい日が決まったら早めに購入するのが安心です。
また、紙のチケットだけでなく、スマートフォンアプリを使って電子チケットを表示・管理するスタイルも広がっています。アプリではチケットの管理に加え、会場マップや最新の混雑状況、イベント情報の確認などもできるので、インストールしておくと便利。さらに、家族や友人とチケット情報を共有できる機能もあり、グループで行動するときにも活躍します。
チケットの準備は、入場をスムーズにするだけでなく、当日の安心感にもつながります。前日にはチケットの確認とアプリの動作チェックをしておきましょう。
電車・バス・車で行く場合の注意点
- 電車:大阪メトロ中央線の延伸で夢洲まで直通予定ですが、終電時間や乗り換えルートの確認は必須です。特に帰りの時間帯は、多くの来場者が一斉に駅へ向かうため、かなりの混雑が予想されます。事前に帰りの時間を逆算して行動すると安心です。駅構内のトイレや売店の位置もチェックしておくと、急なトラブルにも対応できますよ。
- バス:シャトルバスや臨時バスの運行が予定されており、乗り場が複数設けられる可能性があります。行きと帰りで乗り場の場所が異なる場合もあるので、当日案内表示や係員の指示に従うことが大切です。また、混雑を避けたい方は、ピーク時間をずらして移動するのがおすすめ。バスの運行状況はスマホでリアルタイム確認できるアプリの利用が便利です。
- 車:マイカーでの来場は基本的に推奨されていませんが、どうしても必要な方はパーク&ライドの利用を検討しましょう。夢洲周辺の駐車場は数が限られており、事前予約制になる可能性があります。さらに、交通規制や渋滞の発生も見込まれているため、時間にかなりの余裕をもって出発することをおすすめします。車内で待機する時間を想定して、飲み物やタオル、モバイルバッテリーを用意しておくと安心ですよ。
事前に知っておくべき「入場ルール」と検査の流れ

チケット予約時間と入場時間の関係をチェック
万博のチケットには「入場予約時間」が記載されていますが、これはあくまで“検査場に到着する目安の時間”という位置づけです。たとえば10:00のチケットを持っている場合、10:00からの展示開始ではなく、「10:00には検査列に並んでくださいね」という意味になります。実際の入場には、検査や混雑状況などによって多少の時間差が生じることも。
もちろん多少の遅れであれば入場は可能ですが、混雑がピークになる時間帯(特に午前中や土日祝日)は、検査に30分以上かかることもあります。スケジュール通りに会場内をまわるためにも、予約時間の15分〜30分前には到着しておくのが理想的です。
通期パス利用者は「顔認証登録」を忘れずに
通期パスをお持ちの方は、「顔認証」の事前登録が必須になります。これは不正利用や混雑緩和のための対策で、スムーズな入場を可能にしてくれる仕組みです。
登録は公式アプリまたは専用サイトから簡単に行うことができ、スマホで撮影した顔写真をアップロードするだけ。登録後は、入場時に自動で顔認証ゲートを通過できるようになり、手続きがスピーディに。
なお、登録した顔写真と大きく異なる髪型やメイクをしていると認証に時間がかかる場合があるため、当日はできるだけ近い印象で来場することをおすすめします。前髪の位置や眼鏡の有無もチェックポイントになるので、写真を撮る際はナチュラルなスタイルがベターです。
スムーズな入場のための“時系列シミュレーション”
実際の流れを事前にイメージしておくと、当日あわてず行動できます。
- 到着(40〜30分前):夢洲駅やバス降車場から検査場まで徒歩移動。トイレや飲み物の準備もこのタイミングで。
- 検査列に並ぶ(30分前):検査場に到着。列の状況によって待機時間が変動します。
- 手荷物検査(20分前):金属探知ゲートや目視による確認。スプレー類や危険物がないかチェックされます。
- チケット確認(10分前):QRコードを提示。画面の明るさを上げておくとスムーズです。
- 入場完了!:いよいよ万博の世界へ♪
少し早めの行動を心がけるだけで、気持ちにも時間にも余裕が持てます。
検査をスムーズに通過するために今できる準備とは?

QRコードは“すぐに表示できる状態”で準備
QRコードは、チケット確認の際にスマートに提示できるかどうかで、入場のスムーズさがぐんと変わります。公式アプリやメールでチケットを表示する場合、あらかじめアプリを開いておいたり、ブックマークしておくことで、慌てずに済みます。また、読み取りエラーを防ぐために、スマホの画面の明るさは最大に設定しておきましょう。
通信状況が悪い場所や回線が混み合っているタイミングでは、ページの表示に時間がかかってしまうことも。そんなときのために、事前にQRコードのスクリーンショットを撮って、写真アプリに保存しておくのがおすすめです。スクショなら電波が入らない場所でも安心して提示できますし、電池残量が少ないときにもすばやく対応できます。
飲み物は未開封のペットボトルがおすすめ
当日の持ち物として欠かせないのが飲み物ですが、手荷物検査では“未開封のペットボトル”が基本となります。開封済みのものは中身の安全確認ができないため、残念ながら没収の対象となってしまいます。また、凍らせたペットボトルも、内容物の確認が難しいという理由で持ち込みができないことがあります。
おすすめは、常温か冷えた状態の未開封ボトルを持参すること。暑さ対策としては、保冷バッグに入れて持ち運んでも◎。また、飲み終えたあとの空ボトルを捨てる場所が限られていることもあるので、折りたたみ可能なマイボトルと併用するのも賢い方法ですよ。
スプレー缶、金属類、服装でのNG例
手荷物検査では、スプレー缶や金属類などのアイテムが特にチェックされます。検査ゲートでの引っかかりを避けるためにも、以下の点を意識して準備しましょう。
- ヘアスプレー・日焼け止めスプレー:容量にかかわらず、スプレー缶タイプはすべて持ち込み不可です。代わりに、ミストやジェルタイプの日焼け止めを用意すると安心です。
- 大きな金属ベルト:装飾の多いベルトやバックル部分が大きいものは、金属探知機で反応しやすいため避けるのがベター。シンプルな布製ベルトに替えるのがおすすめです。
- ポケットの小銭や鍵:服のポケットに金属類が入っていると検査のたびに取り出す必要があるため、すべてバッグにまとめておくと時短になります。
そのほか、アクセサリーや時計なども事前に外しておくと、よりスムーズに検査を通過できます。服装も検査のしやすさを意識して、シンプルで動きやすいスタイルにしておくと快適ですよ。
持ち物はバッグに“分類収納”しておくと時短に
持ち物は、ただ詰め込むだけでなく「分類収納」しておくことで、検査時の時間短縮やスムーズな提示に大きく貢献してくれます。たとえば、「ガジェット(スマホ・バッテリー類)」「飲食物(ペットボトル・おやつ)」「衛生用品(ウェットティッシュ・マスク)」など、目的別にポーチや小分け袋で仕分けしておくととても便利です。
透明のビニールポーチなどを使えば、検査員にも中身が一目でわかり、確認の時間がぐっと短くなります。さらに「薬」「日焼け止め」「貴重品」など、よく使うアイテムは取り出しやすい場所にセットしておくのもポイント。バッグの中で物が迷子にならない工夫をしておくだけで、当日のストレスがかなり減りますよ。
お子さま連れの方は、お子さま用グッズをひとまとめにしておくと、自分の持ち物と混ざらず管理しやすくなります。バックパックとサブバッグをうまく使い分けて、快適な持ち運びを目指しましょう。
検査待ちの列をストレスなく過ごす工夫
検査場では、時期や時間帯によっては長時間屋外で並ぶことになることも。そんな待ち時間も快適に過ごすためには、ちょっとしたグッズの持参がおすすめです。
たとえば、コンパクトなハンディファンや首掛けタイプの扇風機は、暑い季節の熱中症対策に大活躍。折りたたみチェアや簡易マットを持っていけば、足腰への負担も軽減できます。
日差しが強い日は、日傘や帽子、サングラスがあると安心。さらに、うちわや冷感シート、冷えピタなどもあるとより快適です。逆に寒い季節は、カイロやブランケットなどを用意すると、体調を崩す心配も減らせます。
また、検査列ではスマホの操作や写真撮影をする方も多いため、モバイルバッテリーを手元に用意しておくのもおすすめです。待ち時間が長くても、工夫次第でリラックスして過ごすことができますよ。
知らずに持ち込むとNG!事前にチェックしておきたい禁止アイテム

意外と忘れがち!キャリーケース・カート類は禁止
旅行気分で来場すると、つい持ち込みたくなってしまうのがキャリーケースやキャリーカート。でも、万博の会場内では安全面や通行の妨げを防ぐために、これらの大型荷物の持ち込みは禁止されています。特に混雑時は足元への接触事故や通行トラブルが起こりやすくなるため、厳しく取り締まられる可能性もあります。
どうしても大きな荷物がある場合は、会場外に設置されているクロークやコインロッカーを活用しましょう。ただし、クロークにもサイズ制限や預かり時間、料金が設定されているため、事前に公式サイトなどで確認しておくのが安心です。また、クロークの混雑状況によっては待ち時間が発生することもあるため、なるべく荷物はコンパクトにまとめておくと行動しやすいですよ。
三脚・自撮り棒も原則NG(例外対応の可能性も)
万博の会場では、多くの方が一斉に行き交うため、安全確保の観点から三脚や自撮り棒の持ち込みは原則禁止となっています。特に長さのある自撮り棒や大型の三脚は、人にぶつかったり倒れてしまったりするリスクが高いため、使用できないことがほとんどです。
ただし、一部のパビリオンやフォトスポットでは、施設側で撮影機材を用意してくれている場合もあります。また、障がい者手帳を持つ方など一部条件下での使用が許可されるケースもあるため、必要がある場合は事前に問い合わせをしておくのがおすすめです。
スマホの撮影には、手持ちタイプのコンパクトなグリップや安定器などを使うと安心。記念写真は周囲の方に声をかけて撮ってもらうのもひとつの思い出になりますよ。
小さな刃物や日焼け止めスプレーもNG対象
「お弁当のカトラリーに使うだけ」「旅行用の小型スプレーだから大丈夫」と思って持参したものでも、万博ではNGとなるアイテムがあります。
たとえば、お弁当用の折りたたみナイフやカミソリは、サイズにかかわらず刃物類として没収されることがあります。また、スプレー缶タイプの日焼け止めや制汗剤なども、可燃性ガスを使用しているため、安全上の理由から持ち込みが禁止されています。
どうしても必要な場合は、ジェルやミルクタイプの代替品を持参しましょう。化粧品類や医療用具で不安な場合は、事前に公式サイトや問い合わせ窓口で確認しておくと安心です。
その他「没収されやすい持ち物」一覧
手荷物検査では、安全のために細かくルールが定められており、意図せず持ってきてしまったものでも没収されてしまうケースがあります。以下は、特に没収対象になりやすいアイテムの一例です。当日慌てないよう、しっかり確認しておきましょう。
- ガラス瓶入り飲料:ガラス製品は割れると危険なため、たとえジュースや水であっても不可です。ペットボトルで代用しましょう。
- アルコール飲料:ビールや缶チューハイなど、アルコール類の持ち込みは禁止されています。会場内での販売も制限される可能性があります。
- ドローン・ラジコン類:会場内での飛行物使用は禁止です。個人利用目的であっても没収対象となるため注意しましょう。
- 花火・爆竹など火薬類:火災や爆発のリスクがあるものは当然持ち込みNG。小型のクラッカー類も含まれることがあります。
- キャンドル・オイルライター:火気を使用するグッズは基本NG。特にオイル式のものは危険物として扱われます。
- 大型バッテリー・充電器:電圧や容量によっては制限されることがあります。一般的なモバイルバッテリーであれば問題ありませんが、不安な場合は事前にスペックを確認しておきましょう。
上記以外にも、主催者の判断で没収される可能性があるアイテムもあります。「これ、大丈夫かな?」と迷ったときは、事前に公式サイトやよくある質問をチェックするのが安心です。
しっかり準備して最高の1日に!持っていくべき持ち物リスト

「持ってきてよかった!」と感じた便利グッズ
実際に訪れた方の声で多かったのが、「あれを持って行って本当に助かった!」という便利グッズたち。荷物に余裕があればぜひ取り入れておきたいアイテムをご紹介します。
- ウェットティッシュ:食事のときや手が汚れたときはもちろん、ベンチの拭き取りや汗を軽く拭くときにも活躍。除菌タイプだとさらに安心です。
- 折りたたみクッション:ベンチや地べたに座る場面が意外と多いため、軽くて小さくたためるクッションがあると便利。休憩の質がぐっと上がります。
- 携帯扇風機(ハンディファン):夏場や混雑時の熱中症対策に。首にかけるタイプや手持ち式のものなど、自分の使いやすいスタイルを選びましょう。
- ビニール袋(数枚):ゴミをまとめたり、濡れたものを入れたりと用途は多彩。小さく折りたためてかさばらないのでおすすめです。
- エコバッグ:パンフレットやお土産などで荷物が増えたときに便利。コンパクトに折りたためるタイプを1つ忍ばせておくと安心です。
スマホ&モバイルバッテリーは必需品!
会場内では、チケットの提示、マップの確認、展示の説明閲覧、写真や動画の撮影など、スマートフォンを使う場面が非常に多くなります。そのため、バッテリーの減りがいつもよりかなり早く感じるかもしれません。
おすすめは、容量が10,000mAh以上あるモバイルバッテリーを1つ持っておくこと。2回分ほどのフル充電が可能なので、複数人でシェアする場合や、1日長時間滞在する際にも安心です。
さらに、ケーブルを忘れてしまわないようにするのも重要ポイント。できればマルチ端子対応のケーブルを用意しておくと、他の人のスマホにも使えて便利です。モバイルバッテリーはバッグの外ポケットなど、すぐに取り出せる場所に収納しておくとスムーズですよ。
支払いはキャッシュレスが基本|交通系ICやQRコード決済を
万博会場では、飲食やお土産購入、交通機関の利用など、あらゆる場面でキャッシュレス決済が主流となっています。現金対応のレジはどうしても人が集中してしまい、長い行列ができる傾向があるため、できるだけ事前に準備しておくことが大切です。
交通系ICカード(Suica、ICOCA、PASMOなど)や、スマートフォンで利用できるQRコード決済(PayPay、楽天ペイ、d払いなど)に対応している店舗が多く、あらかじめチャージや登録を済ませておくと当日スムーズに行動できます。特にチャージ専用機やATMも混雑が予想されるため、前日までに残高確認をしておくと安心ですよ。
また、複数の決済方法を持っておくことで「使えない!どうしよう!」という事態を避けられます。スマホの電池切れに備えて、ICカードなど別手段を併用するのもおすすめです。
歩きやすい靴&季節に応じた服装で快適に
万博の会場はとにかく広く、展示やエリアを巡っていると1日で1万歩を超えることも珍しくありません。そのため、足元の快適さは当日の満足度に直結します。
おすすめはスニーカーやウォーキングシューズなど、しっかりと足を支えてくれる靴。クッション性のあるインソールをプラスすると疲れにくくなります。また、靴擦れ対策として絆創膏を準備しておくのも◎。
服装は、春・秋は朝晩と日中の寒暖差に対応できるよう、重ね着スタイルがおすすめ。夏場は通気性・吸湿性に優れた素材を選ぶと快適に過ごせます。逆に夜は冷え込むこともあるため、薄手の上着が1枚あると安心です。
暑さ・寒さ対策グッズ(ネッククーラー、カイロなど)
開催期間中の気候は変わりやすく、日中は汗ばむ暑さでも夜は冷えるなど、体調管理が難しい時期でもあります。快適に過ごすためには、気温に合わせた対策グッズが欠かせません。
たとえば暑い日には、首に巻けるタイプのネッククーラーや冷却スプレー、汗拭きシートなどがあると便利。保冷剤を仕込めるタオルもおすすめです。日傘や帽子、UVカット素材の上着など、日差しを防ぐアイテムも忘れずに。
寒さ対策としては、貼るカイロや手持ちカイロ、ブランケットがあると安心。特に夜に滞在する予定がある方は、風の強さにも備えて、ウインドブレーカーなど防風効果のある上着も役立ちます。
雨具・着替え・タオルなど“あると安心”なアイテム
天候が不安定な日は、突然の雨にも対応できるように準備しておくと安心です。おすすめはコンパクトに収納できて両手が空くポンチョタイプの雨具。傘よりも動きやすく、混雑した会場でも周囲に気を使わず使えます。
また、靴が濡れたときのために替えの靴下やタオルもあると便利。雨に濡れた場合の着替えとして、Tシャツなどの軽いインナーを持っておくと、体を冷やさずにすみます。
汗対策としてもタオルは重宝しますし、レジャーシート代わりにも使えます。荷物に余裕があれば、大判タオルを1枚入れておくと何かと役立ちますよ。
万が一に備える防災系グッズ(絆創膏・簡易ポンチョなど)
混雑する大規模イベントでは、どんなに注意していても小さなケガや体調不良、急な天候の変化に見舞われることがあります。そんな“もしも”のために、小さくても頼りになる防災系アイテムを備えておきましょう。
- 絆創膏・消毒シート:靴擦れや小さなすり傷にすぐ対応できます。
- 簡易ポンチョ:カバンに常備できる薄手のレインコート。突然の雨でも慌てません。
- スマホ用の防水ケース:雨や汗からスマホを守るだけでなく、飲み物がこぼれたときなどの思わぬ事故にも対応できます。
- 小型ライトやホイッスル:夜の暗い場所や緊急時の呼びかけ用として、100円ショップなどで手に入ります。
ほんの少しの準備が、当日の安心感と快適さにつながります。
子ども連れ・高齢者と行く場合のチェックポイント

ベビーカーは持ち込める?貸出はある?
ベビーカーの持ち込みは可能ですが、会場内はとても広く、また一部の人気エリアや展示ゾーンではかなりの混雑が予想されます。そのため、混雑時には抱っこひもとの併用がおすすめです。抱っこひもを使えば、人混みでもスムーズに移動しやすく、お子さまとの距離も近くて安心です。
また、公式から用意されているベビーカーの貸出サービスもありますが、台数には限りがあり、当日分は早い時間に受付が終了することも。事前予約が可能であれば、公式サイトやアプリから早めに申し込んでおきましょう。借りる場合は、利用時間や返却場所、保証金の有無なども事前に確認しておくと安心です。
授乳室・トイレの場所を事前に調べておこう
小さなお子さまと一緒に来場する場合は、授乳室やベビー対応トイレの場所を事前に把握しておくことが大切です。公式アプリのマップ機能を使えば、現在地から最寄りの授乳室・トイレを簡単に検索できて便利です。
授乳室には、オムツ替えベッドや調乳用のお湯が設置されている場所もあるので、赤ちゃん連れでも安心して利用できます。また、会場内には案内スタッフが多数配置されているため、場所がわからない場合は気軽に声をかけて教えてもらいましょう。混雑しやすい時間帯を避けて、余裕を持ったスケジュールで行動するのがポイントです。
車椅子の貸出・段差対応などバリアフリー情報
会場は多くの方にとって利用しやすい環境を目指して整備されており、主要ルートにはスロープや段差解消のためのスロープ・エレベーターなどが完備されています。車椅子の貸出も行われていますが、こちらも台数に限りがあるため、利用希望の方はなるべく早めの来場、または事前予約をしておくのが確実です。
また、バリアフリートイレや多目的スペースも会場内に多数設けられており、介助者と一緒に使用しやすいよう工夫がされています。展示エリアによっては段差のある場所もありますが、その際はスタッフがサポートしてくれる場合もあるため、不安がある方は事前に相談しておくと安心です。ユニバーサルデザインが意識された会場づくりになっているので、高齢の方や身体が不自由な方も、快適に楽しむことができます。
スムーズな退場・帰宅のためにできること

混雑ピーク時間と避け方
閉場直後の19:30〜21:00は、会場全体が一気に帰路につく来場者で非常に混雑します。特に出口付近や交通機関の乗り場周辺は、人の波でなかなか前に進めないこともあります。展示をすべて見終えたあとに「最後にグッズを買おう」と思っていても、同じことを考えている人が多く、レジ前に長蛇の列ができてしまうことも。
そんなときは、グッズ売り場を先に回っておく、あるいは昼食の時間を少し遅らせて、空いているタイミングで展示を楽しむなど、時間の使い方を少し工夫してみるとスムーズです。また、19時前には出口方向に向かい始めると、比較的ゆとりを持って帰宅ルートに乗れる可能性が高まります。
帰り道でもキャッシュレスが活躍
帰りのシャトルバスや船などの臨時交通機関では、チケットの購入や乗車の手続きにキャッシュレス決済が導入されているケースが多く、小銭や紙幣を用意する手間がかかりません。事前にチャージした交通系ICカードや、スマートフォンでのQRコード決済を活用すれば、混雑の中でもスピーディに支払いを済ませることができます。
特に終電間際やバスの最終便が近い時間帯には、少しでも早く移動したいもの。事前に決済手段を複数用意しておくと、読み取り不良や残高不足といったトラブルにも柔軟に対応できます。帰路の途中で軽食や飲み物を買うときにも、キャッシュレスが役立ちますよ。
余裕があれば“周辺の休憩スポット”をチェック
会場を出たあとも、人が一気に移動する時間帯には、公共交通機関の駅構内やバス乗り場周辺はかなりの混雑になります。そんなときにおすすめなのが、夢洲近隣にある休憩できるカフェや飲食施設で、少し時間をずらしてから帰路に着くという方法です。
少し歩いた先にあるテラス席のあるカフェや、眺めのいいレストランなどでひと息つけば、疲れた体もリフレッシュできます。時間に余裕がある方は、あえて人混みのピークを避けて行動することで、心にも余裕を持って1日を締めくくることができますよ。
会場内での過ごし方|楽しむための工夫いろいろ

展示の回り方にコツあり!マップを事前チェック
万博の展示は見どころがたくさんあり、事前にどこを回りたいかを決めておかないと、あっという間に時間が過ぎてしまいます。特に人気のパビリオンは、開場直後の午前中や、夕方以降の時間帯の方が比較的空いている傾向があります。混雑を避けて快適に楽しむには、そうした時間帯を狙って動くのがポイントです。
また、公式アプリではリアルタイムの混雑状況が確認できるので、移動中に情報をチェックしながら次の行き先を調整するのもおすすめ。紙のマップを持っておくと、スマホの電池が切れたときでも安心です。ルートを組むときは、「体験したい展示」「休憩を入れたいタイミング」「トイレの場所」なども含めて、無理のないスケジュールを立てておくと安心ですよ。
休憩スペースやカフェの場所を把握しておこう
広い会場内を歩き回っていると、思っている以上に体力を消耗します。そんなときに重要なのが、休憩できる場所を事前に把握しておくこと。ベンチや日陰のある休憩エリアは限られていて、混雑時はなかなか空きが出ないこともあるため、こまめな休憩計画を立てておくのがコツです。
また、会場内にはフードトラックやカフェも点在しており、ランチやスイーツを楽しむこともできます。フードトラックは回転率が高く、軽食をさっと済ませたいときにぴったり。混雑を避けるためには、ランチタイムを少し早める、または遅らせるのもひとつの手です。お気に入りのメニューを見つけるのも楽しみの一つですよ♪
SNS映えスポットやおすすめフォトスポット
万博会場には、思わず写真を撮りたくなるようなフォトジェニックな場所がたくさんあります。特に夕暮れ時の観覧車や、水辺エリアのライトアップは、ロマンチックで印象的なシーンが撮れると話題です。夜になると建物やオブジェがライトに照らされ、昼間とは違った雰囲気に変わるのも見どころの一つ。
ただし、三脚の使用は禁止されているため、スマホ用のグリップやスタビライザーがあると、手ブレの少ない写真が撮りやすくなります。撮影の際は、通行の邪魔にならない場所を選んで、安全第一で楽しみましょう。思い出の一枚を残すためにも、カメラの準備は万全にしておくのがおすすめです!
【体験談】実際に行ってみた人の声・気づきまとめ
「もっと早く知っておけば…」体験者のリアルな後悔ポイント
万博を訪れた人たちの声を聞いてみると、「これだけは事前に知っておきたかった…!」という後悔の声もちらほら。そんなリアルな体験談から学べることはたくさんあります。
- 検査列で日焼けした:屋外の待機列では日差しを遮る場所が少なく、思いのほか日焼けしてしまったという声が。日傘や帽子、日焼け止めの事前準備は必須です。
- モバイルバッテリーを忘れて写真が撮れなかった:写真撮影やマップ確認でスマホを頻繁に使うため、電池の消耗が早くなりがち。バッテリーが切れて、大事なシーンが撮れなかったという人も。
- フードトラックの行列が想像以上:ランチタイムのピークに並んでしまい、1時間以上待った人も。時間をずらす、軽食を持参するなどの工夫が必要です。
- トイレの場所を確認しておらず焦った:会場が広いため、トイレを探すだけでも時間がかかることがあります。事前にマップでチェックしておくのが◎。
「これは持って行って正解だった!」便利グッズ体験談
実際に万博へ行った人たちが「本当に持って行ってよかった!」と感じたグッズには共通点があります。それは、“小さな不便を解消してくれる”という点です。
- ハンディファン:夏場の暑さ対策に大活躍。首掛けタイプやUSB充電式など、自分に合ったものを選ぶと快適さが違います。
- 折りたたみクッション:座る場所が限られている中で、少しの休憩時間も快適に過ごせたと好評。
- ネッククーラー:冷却機能があるものは、猛暑でも体温上昇を防げる心強いアイテム。
- モバイルバッテリー(2ポート):同行者と一緒に使えるタイプだと助かるとの声も。
- 除菌シート&ポリ袋:衛生対策と荷物の整理に便利。お土産用の小分け袋にも使えるとのこと。
検査で意外に時間がかかった話・混雑時間の傾向
手荷物検査はスムーズに通過できることもあれば、天候や来場者数によって想像以上に時間がかかる場合もあります。体験談では以下のような傾向が見られました。
- 雨の日や連休初日は検査が長引く傾向:傘やレインコート、濡れた荷物などの影響でチェックに時間がかかるそうです。
- 朝イチは比較的スムーズでも、午前10〜11時以降は列が長くなることも。
- セキュリティ強化日や外国要人の来場時などは検査がより厳しくなり、通過までに時間を要したという声も。
時間に余裕を持って行動することと、混雑しそうな時間帯を避ける計画が、快適な1日を過ごすカギになります。
当日の持ち物チェックリスト|印刷して使えるチェック表つき!
入場前に再確認!忘れ物チェックリスト
忘れ物があると、せっかくの1日が台無しになってしまうことも。出発前にしっかりと見直して、準備万端で会場へ向かいましょう。以下は、基本のチェックリストに加え、あると便利な「プラスαアイテム」も取り入れた充実版です。
- チケット(QRコード)※スマホアプリやメールで表示できるようにしておくか、スクショ保存がおすすめ
- スマホ&モバイルバッテリー(10,000mAh以上、ケーブルも忘れずに)
- キャッシュレス決済手段(ICカード、QRコード決済アプリ、予備に現金少々)
- 未開封ペットボトル飲料(凍らせたものはNGなので常温または冷えたものを)
- タオル&ハンカチ(汗拭き・雨対応・レジャーシート代わりにも)
- 折りたたみ傘 or ポンチョ(両手が空くポンチョタイプが特に便利)
- 絆創膏など救急セット(靴擦れ対策、消毒シートや予備マスクもあると安心)
- ウェットティッシュ&除菌シート(食事前や手すりを触ったあとに活躍)
- ゴミ袋またはビニール袋(ゴミを持ち帰る用、お土産の小分けにも)
- 折りたたみクッション(地面やベンチが硬い場所での休憩用)
- 防寒具・カイロ(夜の冷え対策に)/日焼け止め・帽子(日中の紫外線対策に)
このリストを印刷してチェックできるようにしておくと、準備時にも心強いですよ♪
家族で行くならそれぞれの持ち物を分担しよう
家族でのお出かけは、どうしても荷物が多くなりがちですよね。そんなときは、ひとりにすべてを任せるのではなく、みんなでうまく分担するのがポイントです。たとえば、大きめのバックパックには共用のアイテム(飲み物、レジャーシート、救急セットなど)を入れ、ショルダーバッグにはそれぞれの貴重品やスマホ、モバイルバッテリーなどの個人用アイテムを入れると効率的です。
お子さまにも、小さなリュックを持たせて、軽めのおやつやハンカチなどを入れてもらえば、自分の荷物を持つという責任感にもつながります。パパとママで役割を決めて「移動担当」「スケジュール管理担当」などと分けるのもおすすめ。こうすることで、現地での負担が偏ることなく、みんながストレスなく楽しめる1日になりますよ♪
【Q&A】よくある疑問をまとめて解決!
入場にかかる平均時間は?
混雑が予想される土日祝日やイベント開催日などでは、入場までに30分から60分程度かかることが多く、場合によってはそれ以上の待ち時間が発生することもあります。特に午前10時以降は来場者が一気に増える傾向があるため、開場直後を狙うのがおすすめです。一方で、平日の早朝(開場直後)であれば比較的スムーズに入場でき、15分程度で検査を終えられるケースも。QRコードの準備や持ち込み禁止物の確認など、事前準備がしっかりできていれば、検査もスムーズに進みやすくなります。
一度外に出たら再入場できる?
基本的には一度退場すると再入場は認められていませんが、体調不良や緊急時など、やむを得ない事情がある場合には、スタッフに相談すれば柔軟に対応してもらえることもあります。再入場には手続きが必要なケースもあるため、事前に入場口や総合案内所で確認しておくと安心です。また、再入場の証明としてリストバンドや再発行されたQRコードが必要になることもあるので、その点も覚えておきましょう。
赤ちゃん連れでも大丈夫?
赤ちゃん連れでも安心して過ごせるよう、会場内には授乳室やおむつ替えスペースが各所に設けられています。場所によっては調乳用のお湯や個室ブースも完備されており、プライバシーを確保しながら安心して利用できます。さらに、公式のベビーカー貸出サービスも用意されていますが、台数には限りがあるため、できるだけ早めの時間に受付するか、事前予約できる場合は活用しましょう。また、ベビーカーのまま入れるパビリオンもありますが、混雑時には抱っこひもがあるとスムーズに移動できて便利です。
体が不自由な方のサポート体制は?
会場では、身体に障がいのある方や高齢者の方でも快適に過ごせるよう、多彩なサポート体制が整えられています。たとえば、バリアフリー設計のルートやスロープ、車椅子対応のエレベーターが随所に設置されています。また、ユニバーサルデザインのトイレは広めの設計になっており、介助者と一緒でも安心して利用できます。さらに、視覚障がい者向けの音声ガイドや、聴覚障がい者向けの表示サインなど、さまざまなサポートが用意されており、必要に応じて事前に相談窓口に連絡しておくと、よりスムーズに案内してもらえることもあります。
まとめ|準備万端で、心にも余裕を持って楽しもう
持ち物は“安心感”をくれる最大の味方
忘れ物がないだけで、当日のストレスはぐっと減ります。急なトラブルや予期せぬ出来事があっても、「あ、あれ持ってきててよかった」と思えるだけで気持ちが落ち着きますよね。特に暑さ・寒さ対策や衛生用品、ちょっとした応急グッズがあると、体調面でも安心です。小さな準備が「万が一」にしっかり対応してくれる頼れる存在になります。
リストを活用して抜かりなく準備することはもちろん、チェック表にメモ欄を作って自分だけの工夫を加えるのもおすすめ。自分や家族の生活スタイルに合わせてカスタマイズしておけば、当日もさらにスムーズに行動できますよ。
当日も前向きな気持ちで迎えるために
会場に向かう道中や入場待ちの時間も、ポジティブな気持ちで過ごせるようにしておきたいですよね。そんなときに大切なのが、時間に余裕を持ったスケジュールと、ちょっとした楽しみを事前に用意しておくこと。たとえばお気に入りの音楽を聴きながら移動したり、お子さんと一緒に「今日は何を楽しみにしてる?」なんて会話をするだけでも、気持ちがグッと明るくなります。
「ちゃんと準備できた!」という自信は、心にも余裕をくれます。焦らずに行動できれば、周囲にもやさしく接することができて、より素敵な思い出が増えていくはず。ぜひ、当日はあなたらしく前向きな気持ちで、特別な一日を思いきり楽しんでくださいね♡